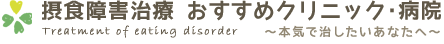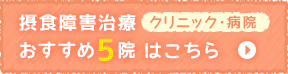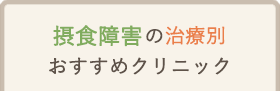摂食障害の入院治療とは?
過剰に食べ続けてしまう過食症や過食嘔吐は、放置するとカラダに深刻な影響も!
摂食障害の入院治療とは?

チームで治療に当たる摂食障害の入院治療
摂食障害の治療には、心理教育・病態把握・身体治療・心理療法などさまざまな治療方法が用いられます。摂食障害により、低体重で体力が低下するなど、深刻な身体症状が合併症としてみられる場合には、入院による治療を行うことがあります。
摂食障害の入院治療はどんな時に必要で、どんな流れで治療が行われるのでしょうか。
入院治療が必要なケース
摂食障害の治療において、入院が必要と判断される基準はいくつかあります。日本摂食障害学会が監修する「摂食治療ガイドライン」には、入院適応の目安として次の6つの目安が記されています。
- 極端な羸痩(るいそう)
- BMI14以下
- 標準体重の65%以下
- 身長に関わらず30kg以下
- 最近、低血糖発作を起こした
- 歩行障害
- 重度の低血圧
- 重度の徐脈:50/分以下
- 重篤な合併症がある
- 「摂食治療ガイドライン」監修:日本摂食障害学会
重篤な合併症とは、感染症や腎不全、不整脈、心不全などを指します。
入院治療の目的
摂食障害が進行し、体力が低下したり合併症が深刻だったりした場合、命を落とす危険もあります。入院治療の目的の一つは、
生命の危機にある患者の命を救うため
の、緊急入院です。また、外来治療ではなかなか体重増加が見られなかったり、迅速に体重を増やす必要があったりする場合には、栄養療法や行動療法を用いながら、目標体重に達するまで入院治療を行います。
もう一つの入院の目的は、食行動の是正です。過食性嘔吐や下剤を使うことが日常になってしまった方は、食事の量はどの程度が適正なのかが、わからなくなりがちです。
こうした場合に期限を決めて、入院環境で規則正しい食生活を送る練習をします。
入院期間
摂食障害の入院治療は、入院目的によって異なります。体重増加が目的の場合は、目標体重に達するまで入院を続けることとなります。
ただし、患者さんの都合などにより入院日数を短縮したいという要望がある場合には、入院を何回かに分けて治療を継続します。
食行動の是正が目的の入院治療の場合は、通常2週間の入院期限を設けることが多いようです。
入院治療の流れ
摂食障害の治療で入院。そう病院で言われたら、どのような治療が行われるのか、不安に感じる方もいらっしゃると思います。大まかな入院治療の流れがわかれば、心構えもできて安心ですよね。
入院当日
入院当日は、入院時に行われる治療の説明と注意事項が説明されます。
その後、栄養状態のチェックや病歴の確認、血液検査や尿検査、便検査、心電図、X線写真などの検査を行います。
また、初期輸液として3時間ほどの点滴で、ビタミンB製剤などを点滴します。
その他、入院中はどんな風に過ごせばいいのかの説明を受け、栄養療法などが始まります。
入院1〜4日
入院第1期となる1〜4日目は、毎日血液検査や尿検査を実施します。
また、1日おきに体重測定を実施し、治療の進捗をチェックします。血液検査の結果を受けて、点滴治療や内服薬の服薬などを行います。
入院期間中の食事は、基本的に30分以内に全部食べなければなりません。万が一食べられなかった場合には、次の食事から経管栄養に切り替え、2週間ほど継続した後、再び通常の食事に戻ります。
入院5〜10日
入院第2期となる5〜10日目は、行動制限療法の準備を始めます。食事も7日目には1000kcal食、10日目には1200kcal食というように、少しずつカロリー量を増やしていきます。
入院第1期と同じように、食事が一度でも食べきれなければ、経管栄養に切り替えられます。
この期間に医師から退院時の目標体重を設定、説明してもらうことが多いようです。
入院11〜28日
輸液療法が終了し、バイタルサインや意識レベルが安定したら、行動制限療法をスタートします。行動制限療法(認知行動療法)とは、体重の増加にあわせて行動制限を一つずつ外していく方法です。
体重が増えることで、できることが増えるため、達成感を感じ、病気を克服するモチベーションも高まります。行動制限療法は、前向きに治療を進めるための大切なステップです。
入院29日〜
BMIが16を超えたら、徐々に退院に向けた準備を進めます。
外食や外泊訓練、栄養指導などを受けながら、退院後の生活について話し合います。
入院治療を成功させるための心構え
摂食障害の入院治療は決して短くありません。行動制限療法(認知行動療法)は患者さんによってプログラム内容も別個に作る必要があり、患者さんのことをきちんと見てくれる医師や栄養士の存在が欠かせません。
入院中は体重増加の程度をチェックしながら、摂食障害を克服するために必要な知識なども学んでいきます。
摂食障害は、患者さんと医師との意思疎通や信頼関係が、何よりも大切です。患者さんが未成年の場合には、家族に対するケアも必要となってきます。
だからこそ、信頼できるクリニックを選ぶことが大切です。
参考:『摂食障害ハンドブック』東京大学医学部附属病院 心療内科
http://psmut.umin.ac.jp/ed.pdf
合わせて読みたい~体験談
関連ページ:低血糖症の検査・治療を行う栄養療法