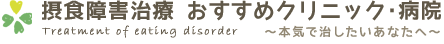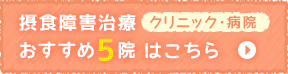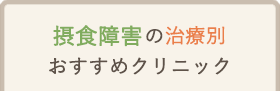摂食障害にはどんな種類があるのか
摂食障害の種類や判断基準とは
症状が様々な摂食障害。その種類や判断基準はどのようなもの?

“摂食障害”と聞くと、よく知られている「拒食症」や「過食症」くらいだと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、摂食障害には様々な種類があり、それぞれに異なる特徴があります。自分では摂食障害ではないと思っていたとしても、何らかの種類に当てはまることがあるかもしれません。ここでは、摂食障害の種類やその判断基準などについて説明します。
「DSM-IV」と「ICD-10」について
摂食障害について医療機関での診察を受ける場合、医師は患者の体のやせ具合や、むくみや吐きダコの有無などをチェックして、会話の中からも症状について観察していきます。そして、医学的に定められた診断基準を使用し、摂食障害の種類について判断していきます。
現在主に用いられている診断基準は、「DSM-IV」と「ICD-10」というものです。「DSM-IV(精神疾患の分類と診断の手引き)」はアメリカ精神医学会で、「ICD-10」はWHO(世界保健機構)で定められている基準です。一般的に、DSMは精神的疾患を分類する際、ICD-10は疫学的に分類する際に用いられることが多くなっています。
DSM-IV-TRによる摂食障害の種類と基準
神経性無食欲症の判断
神経性無食欲症とは、いわゆる“拒食症”のことを指します。それをさらに「制限型」と「むちゃ食い・排出型」の2つに分類し、診断基準によって症状を見極めていきます。
- 1.年齢や身長に対して正常である体重の最低限、またはそれ以上になることを拒否
- 2.体重が不足しているのに、体重が増えることや肥満になることに対して強い恐怖を持っている
- 3.自分の体重や体型の感じ方、自己評価がゆがんでいる(明らかに痩せているのに太っていると思いこむなど)
- 4.初潮後の女性の場合、無月経が起こっていないかどうか
これらの基準を診察したうえに、食事をした後に嘔吐や下剤・利尿剤の使用をおこなっていないかなどを加えて判断していきます。
神経性大食症の判断
神経性大食症は、いわゆる“過食症”のことです。これをさらに「排出型」と「非排出型」に分類しています。
- 1.むちゃ食いを繰り返している(他の人が食べるより明らかに多い食べ物を食べる、食べることをやめられなかったりどれだけ食べているのかを制御できないなど)
- 2.体重が増加することを防ぐために、適切ではない代償行動をとる(自分で嘔吐したり、下剤や利尿剤や浣腸などを使用する、絶食や過剰な運動をしたりなど)
- 3.1や2の行動を、平均して少なくとも3ヶ月間にわたり、週2回起こしている
- 4.自分に対しての評価が、体型や体重の影響を過剰に受けている
- 5.障害は神経性無食欲症のエピソード期間中にのみ起こるものではない
これらの基準を使用し、神経性大食症の診断や、そのなかでも「排出型(不適切な方法で食べ物を定期的に排出している)」と、「非排出型(排出行為が定期的ではない、もしくは絶食や過活動のみ行う)」のどちらかなどを判断していきます。
診断基準にあてはまらない摂食障害
DSM-IVにおいて、神経性無食欲症や神経性大食症の診断基準を満たさない場合、「特定不能の摂食障害」という診断をします。基準は次の通りです。
- 1.他の神経性無食欲症の基準をすべて満たしているが、定期的に月経がある(※女性の場合のみ)
- 2.他の神経性無食欲症の基準をすべて満たしているが、著しい体重減少があっても現在の体重が正常範囲内にある
- 3.他の神経性大食症の基準をすべて満たしているが、むちゃ食いと代償行為の頻度が週2回未満・持続期間が3カ月未満である
- 4.代償行動を定期的におこなっているが、正常体重であり食事量が少量(クッキーを2枚食べただけなのに自発的に嘔吐させるなど)
- 5.大量の食事を噛んで、飲みこまずに吐き出すという行動を繰り返す(チューイング)
- 6.むちゃ食いを繰り返すが、神経性大食症で特徴的である不適切な代償行動をおこなわない(むちゃ食い障害)