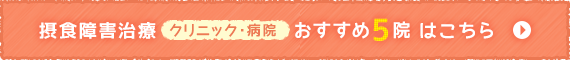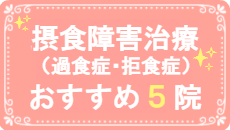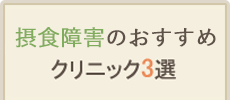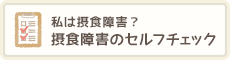厚生労働省の難治性疾患(難病)に指定された摂食障害

中枢性摂食異常症について
「飲み込む力が低下して食べられない」など身体の機能の低下に伴う摂食障害と、いわゆる拒食症や過食症などの摂食障害を区別するために、このページで紹介している摂食障害は『中枢性摂食異常症』と呼ばれる摂食障害を紹介しています。
日本では、1981年に中枢性摂食異常症(摂食障害)が難病(特定疾患)として指定され、治療法の研究などが進められました。残念ながら、平成27年7月以降、摂食障害は障害者総合支援法の対象外となり、医療費助成などが受けられる障害者総合支援法の対象疾病からは外れてしまいました。しかしながら、依然として一度かかると治療に長い時間を必要とする病気であることに変わりはありません。
厚生労働省の指定する難病とは?
厚生労働省が指定する難病とは、平成27年1月から施行された難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づくもので、医療費助成や治療法の研究などに国の予算が投じられる病気です。
難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)施行前は、特定疾患治療研究事業として同様の施策が行われていました。
難病法では、指定難病にするための条件として、次の4要件が定められています。
- ・発症の機構が明らかでない
- ・治療方法が確立していない
- ・希少な疾患
- ・長期の療養を必要とする
さらに、患者数は人口の0.1パーセント(12万人強程度)であることや、客観的な診断基準があることなどが指定難病になる基準となっています。
難病法では、難病の中でも「指定難病」として診断されて、重症度が一定異常の場合に、医療費助成が受けられることとなっています。ただし、摂食障害は、2018年1月時点で指定難病となっていませんので、残念ながら医療費助成は受けられません。
難病指定になって進められた摂食障害研究
摂食障害が難病に指定されたのは、1981年。その後、研究や疫学調査、さらに日本摂食障害学会の設立など、日本でも摂食障害の治療に対する体制作りが進められてきました。
日本国内では,摂食障害は,1981年に難病(特定疾患)の指定を受けた.現在(2007年),厚生労働省は難病(特定疾患)123疾患を指定しており,摂食障害も「中枢性摂食異常症」として指定され調査が継続されている.2005年には日本摂食障害学会も設立され,現在もなお,さまざまな研究が進められている.
出典:『回復体験記から見る回復者自身による摂食障害解釈』中村,社会学評論,58(4)
これに伴い結成された、中枢性摂食異常症に関する調査研究班は、摂食障害が発症した原因や治療法などの研究を進め、次のような研究成果・活動をおこなってきました。
神経性食欲不振症(拒食症)の治療薬にグレリンの可能性を見出す
厚生労働省科学研究費補助金により行われた難治性疾患克服研究事業「中枢性摂食異常症に関する調査研究」にて、平成18年に神経性食欲不振症患者におけるグレリンが栄養状態の改善に対して効果があることが報告されました。
1999年に発見されたグレリンは、食欲を亢進させる作用のある物質です。
脳の成長ホルモンの分泌を促進する物質の受容体に作用。成長ホルモンが分泌されるのを促進する効果があることなどが同研究で明らかになっています。
グレリンが摂食促進作用,胃の蠕動運動促進作用を有することから,グレリンの神経性食欲不振症の病態改善効果が期待される.実際,罹病期間が長く,なんとか治りたいという気持ちを持った入院中の本症例にグレリンを朝食前と夕食前に静脈内投与したところ空腹感が増し,摂食量が増すことが確認されている.
さらに退院後に体重増加が認められている.これらの結果から,グレリンの胃の蠕動運動促進作用により上腹部の不快感が消失し,摂食量が増し,それが契機となり摂食量の増加が維持されて体重増加につながったと考えられる.これらの結果はグレリンが本症の治療薬として使用されうる可能性を示すものと考えられ,今後の発展が期待できる.
出典:『神経性食欲不振症の神経内分泌学的病態(4)』芝﨑,日医大医会誌 2008; 4(3)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/manms/4/3/4_3_148/_pdf/-char/ja
治療・診療体制の整備
この他にも、研究班は「神経性食欲不振症のプライマリケアのためのガイドライン」を2007年に作成したり、患者の家族のための教育用DVDを作成したりと活動を進めていました。
難病指定から外れても受けられるサポート制度
現在、摂食障害は難病指定ではないものの、長期にわたり症状に苦しむ方がいること。生活の質を著しく低下させ、最悪の場合死に至る病気であること、摂食障害について相談できる病院や期間がまだまだ少ないことなどから、摂食障害治療支援センターの設置運営事業がスタートしています。
摂食障害の患者さんが利用できる制度には「自立支援医療(精神通院医療)」「精神障害者保健福祉手帳」「高額療養費」などの制度があります。
また、宮城県・福岡県・静岡県には摂食障害治療支援センターが設置されています。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患に苦しむ方に対する、通院治療費用のサポート制度です。
世帯収入によって、治療費の自己負担額の上限が決められます、また、通常であれば治療費や薬代は3割負担が原則ですが、自立支援医療(精神通院医療)に認定されれば、原則1割負担で治療を受けることができます。
自立支援医療(精神通院医療)に認定してもらうためには、かかりつけ病院で作ってもらった診断書を、住民票のある市区町村役場の窓口に提出・申請が必要です。
精神障害者保健福祉手帳
同じく、精神疾患の方を対象に作られている精神障害者保健福祉手帳。病気により生活や社会活動に制約がある場合、公共料金の減免や税金控除などの社会的優遇が受けられたり、障害者枠求人への応募などができたりするようになります。
申請には、自立支援医療(精神通院医療)と同じく診断書が必要です。ただし、申請できるのは病院にかかった日から半年以上経っている必要があります。
生活面での不安を少しでも軽減し、治療に専念できるようにするためにも、該当する方は是非、市区町村の担当窓口に相談してみましょう。
高額療養費
時には入院治療も必要となる摂食障害。医療費が高く、「どうしよう」と不安を感じる方もいるかもしれません。高額療養費制度は、月初から月末までの間に支払った医療費が一定額以上になった場合、上限額を超えた分、払い戻しが受けられる制度です。
医療保険の担当窓口で申請できますので、入院が必要になった場合などは、ぜひ確認してみましょう。
参照:厚生労働省,みんなのメンタルヘルス総合サイト(高額療養費制度)
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_05_01aid.html(2018年1月8日時点)