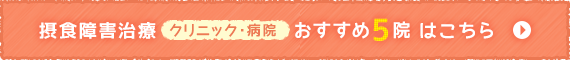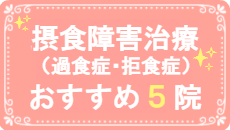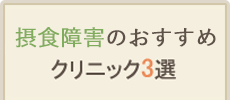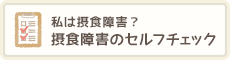価値観を整える、認知行動療法

対話をしながら体重や体型に関しての歪んだ価値観を見直し改善していく治療法
認知行動療法とは、体重やスタイルについて「こうでなければ!」と凝り固まってしまった考え方をやわらかくほぐして、「やめたい」と思っている行動を改善できるようにサポートする治療法です。精神療法や心理療法の一種で、薬や手術ではなく医師と患者の対話を通して改善を目指します。
ストレスを受けてネガティブな感情に捕らわれた時にどのように考えるのか、その思考は現実とどれだけ差があるのかを知ることで適切に自分を評価できるようになり、行動を変えられる治療法です。
患者さんの考え方を見直す
摂食障害で悩む人の中に多いのが「認知の歪み」と呼ばれる、適切に判断できない症状。「もっと痩せなければいけない」と強く思い込んでしまい、ダイエットがエスカレートしやすい考え方です。
過食や拒食といった行動に繋がらないようにするには、正しい考え方へ軌道修正する必要があります。摂食障害の症状自体に患者自身が違和感を覚えることはできても、考え方が歪んでいると自ら気付くのはなかなか難しいもの。そこで医療機関では、患者との対話を通して過去・現在において考え方や行動がどう変化していったかにフォーカスをあてて、歪められた認知を修正していきます。
この認知の歪みを改善するために、認知行動療法では3段階の治療が行なわれます。摂食行動異常を正常化させる第1段階、体重や体型に関する認知の歪みを改善することを目標とする第2段階、治療内容を持続・強化する第3段階の治療を実施。時間をかけて摂食障害と向き合っていきます。
この治療で大切なことは患者と信頼関係を築いて同じ目的に向かうこと。医師は患者に治療方法の提案や情報を発信しながら、患者が自発的に「変わりたい」と思って行動する過程を見守ってくれます。そして、患者を励まし勇気づけながら一緒に摂食障害に向き合っていくのです。
認知行動療法の治療内容
認知行動療法は基本的に3段階に分けて治療を行ない、症状を改善していきます。ここでは、段階1~3まで順を追って治療内容について触れていきましょう。
第1段階
第1段階での治療目標は、患者との治療関係を良好にして異常な摂食行動を改善すること。4週間にわたり1週間に1度のペースで患者と対話を行い、下剤の乱用や自発的に嘔吐を行なう行為、大食などの改善を目指します。
1回目の面接
1回目の面接では、患者との会話のなかで病歴を聞き、症状や兆候を解明。患者にも病気のことを説明し、認知行動療法についても理解してもらいます。具体的な問題を提示することで、面接が終了するときにその患者が達成できる課題を提案。達成することができたら褒めて激励します。認知行動療法にとって患者が自分の意志で参加することは大切です。そのため、努力することで成果が必ず得られて病気が改善するということを保証してあげることがポイントになります。
2回目の面接
認知行動療法では、患者に毎日の食行動を記録してもらい、症状に陥りやすい状況を把握。2回目の面接で記録を見ながら一緒に検討していきます。
3~5回目の面接
3~5回目は、患者に対して摂食をコントロールするための行動戦略の提案を行ないます。記録を見ながら出した課題の達成度を検討。1週間に1度でも課題を達成していれば激励することを積み重ねて、患者に自信をつけさせます。さらに達成できる課題を提示しながら、食生活での注意点として下剤や利尿剤を使用しても身体の水分がなくなるだけで脂肪が減るわけではないこと、排出行動で体重調整にならないことを説明。排出行動や大食による身体合併症についても理解してもらいます。
6~8回目の面接
6~8回目でも食行動の記録を確認して達成具合や課題を検討。達成できていなければ新しい行動戦略を立てて達成できるように調整していきます。また患者が症状改善に向けて努力するために、家族と一緒に面接を行なうことも。患者が抱えていることを打ち明けることで罪の意識を減らしていくことが大切になってきます。
第2段階
段階2では主な治療目標を「認知の修正」とし、治療を2週間に1回のペースで実施。16週間にわたって治療を行なっていきます。
9回目の面接では、通院回数が減る第2段階の治療へ移行しても大丈夫かを判断します。10~14回目では、摂食制限の回数が減少しているか、きちんと規則正しい食生活がキープできているかを確認。大食してしまう状況を把握させて、対処するスキルを高めて問題を解決する訓練を行なっていきます。
この訓練を繰り返し練習してもらうことで、問題に直面したときに自分で対処することが可能になってくるのです。そしてここで大切になってくるのが「認知を再構成する」こと。今までの体重や体型についての間違った価値観や摂食障害を持続させてしまう思考などを明確にして、変えていきます。
15~16回目では治療を継続しながらも「治療が終了に向かっている」と伝えて、患者が治療を行なって感じたことを話し合います。
第3段階
第3段階では、6週間かけて2週間に1回の治療を実施。この段階3では、今まで行なってきた治療を通して改善できた状態をキープ、そして今後再発したときに対処できるように準備を行なっていきます。
患者に規則正しい食生活と嘔吐や大食へ向かわない状態を維持させて、今まで学んできた問題の解決方法や認知再構成法を自分自身で実施してもらう段階。食行動を自分でコントロールできるようになり、ダイエットをしない状態まで改善できたら治療終了です。