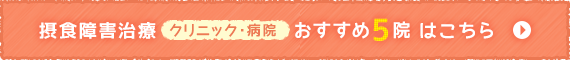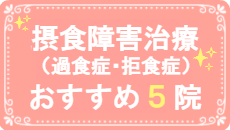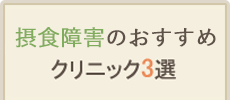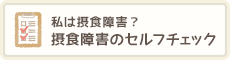ストレスによる拒食症・過食症

ストレスが摂食障害(拒食症・過食症)を引き起こす原因?
最近では、ストレス過多になってしまう生活環境に身を置く人も多いことと思います。
外的要因のストレスなら環境を変えるなどの対処方法がありますが、自分自身で抱える内的要因のストレスは、自分1人で解消することが難しい場合があります。
例えば、周囲から見れば健康的な体形なのに、本人としては「思うように痩せられない」とか、良好な関係を築いている人間関係の輪に対して「本当に仲良くできてるかな?もしかして私は嫌われていないかな?」などの自分を原因とする形のストレスです。
こうしたストレスが増えていくと、食べなくなっていったり、一度に大量に食べるようになったり、食べても吐くことを繰り返てしまったりと、摂食障害になってしまうことがあります。摂食障害の定義からは外れてしまいますが、口に食べ物を含んで良く噛み、飲み込まずに吐き出すチューイング行為も、摂食障害に近い行為です。
ここでは、ストレスによる摂食障害(拒食症・過食症)について紹介します。
ストレスによる拒食症
拒食症を引き起こすストレスは人によって様々。「女性らしい体になることへの嫌悪感や恐怖」「周囲からの目線」「自分は太っていると感じて体重を減らさなければと強迫観念に苛まれる」などのストレスは、拒食症を引き起こす原因としてよく知られていることかもしれません。
しかしながら他にも、「いい成績を残さなければ」「進路で失敗した」「友達との人間関係がうまくいかない」「家庭内のトラブル」などのストレスも、拒食症の原因になることがあります。ストレスにより何らかの不安を感じていると、痩せていることに対して安心感を覚えることがあります。これは、心がストレスに対して導き出した一つの防衛反応でもあるのです。
ストレスによる過食
「ストレスが溜まっていたからむちゃ食いしてしまった」、これくらいは誰でも経験があることなのではないでしょうか。次第にそれが習慣になると、過食嘔吐や拒食症など、さらに色々な症状に発展して摂食障害となってしまうケースも多いです。ここでは、ストレスと摂食障害にはどのような関係があるのかを解説します。
もちろん、ストレスが拒食ではなく無茶食いなどの過食衝動のきっかけとなることもあります。無茶食いをしてストレスを発散する行動は、繰り返せば逆に食べていないと不安になってしまうこともあります。また、痩せなければと過剰に考えて無理なダイエットをした結果、反動で過食に至るケースもあるのです。
きっかけは些細なものだったとしても、一度過食でストレスに対処できると覚えてしまうと、なかなか抜け出せなくなるケースもあります。こうした場合には、ストレスへの対処方法(コーピングスキル)を身につけるための支援が治療においても重要となってきます。
ストレスで過食嘔吐になる原因
過食嘔吐は10代後半から20代の世代の女性に多い症状ですが、近年は10代前半や30代以降などの患者や男性の患者も増えてきています。「自分には関係ない」と思っていた人が、いつのまにか過食嘔吐の症状に陥っていることもあるかもしれません。とある調査では、「過食」自体は女子大生の“6割”が経験しているという報告もあるほど身近な存在です。ストレス発散に「食べる」という方法をとること自体は、決して珍しいものではないのです。
それが「過食嘔吐」に発展してしまう理由の多くは、食べてしまったことに対して“罪悪感”を持つことにあります。とくに、自分の体型に自信がなかったり、コンプレックスがあったりする人に多いです。
「ストレスが溜まっているから美味しいものを食べてリフレッシュしたい!」ということ自体は、とても自然な欲求です。甘いものや美味しいものを食べると幸せな気持ちになりますし、「明日からまた頑張ろう!」という活力にもなります。しかし、それがいつしか「何でもいいからとにかく食べたい」や、「たくさんの量を食べなくてはいけない」という強迫観念に駆られてしまうと問題です。さらに自らの体型に対するコンプレックスや、ダイエット中の焦りなどが加わってしまうと、過食嘔吐に発展することが多くなってしまいます。
最初は「ストレス発散」の手段だった過食ですが、次第に「過食」してしまう自分に対してストレスを抱いてしまうようになってきます。「ストレス→食べる→食べたことに対してのストレス→吐く→吐くことに対してのストレス」…と、なかなか自分では抜け出せない負のスパイラルに陥ってしまいがちです。
症状が過食嘔吐まで発展してしまう人は、もともと「完璧主義」であったり、「自分への理想が高い」人であることが多いです。過食してしまう自分も、それによって太ってしまう自分も許せない!という意識から抜け出せなくなると、過食嘔吐もなかなか辞められなくなってしまいます。
そういった悪循環から抜け出すためには、自分に対してのハードルを下げてあげることや、過食・過食嘔吐以外のストレスのはけ口を見つけてあげることが大切です。とくに、他のストレス発散方法を模索することには大きな意味があります。
ストレスで食べるのが止まらないことがある?
もちろん、ストレス発散方法として、美味しいものをお腹一杯食べたり、お酒を飲んだりすること自体は悪いことではありません。月経前になんだかイライラして甘いものをたくさん食べてしまうというような経験は誰もがしたことがあるのではないでしょうか?女子短大生の過食症傾向を調査した研究では、アンケートに回答した約200名の女子短大生のうち、無茶食いをしたことがあると回答した人の割合は46.1%もいたと報告されています。[1]ストレスで食べるのが止まらないからといって、必ず過食症であるとは限りません。
もしもストレスで食べるのが止まらないなら、心と体が疲れているサインと捉え、食べる時に心にも体にも「幸せ」を感じられるような食事を心がけるといいのではないでしょうか。
過食や過食嘔吐をせずにストレスを発散する対処法
過食に代わる行動を見つける
「食べたい」と思ったら、食べ物を探したり食べたりするよりも素早くできるような、代わりの行動を見つけておくと便利です。例えば、自宅でゆっくりするスペースにお菓子を置くのではなく、ネイルセットやスキンケアのセットを置いてみましょう。「何か食べよう」と食べ物に手を伸ばす前に、ネイルのケアをしてみたり、顔にパックをしてみたりすることがおすすめです。大切なのは“一時食べ物から関心をそらす”ことで、何か別のことをしている間に食べ物への欲求をごまかすことができます。ましてネイルやパックはしばらく食べ物を食べることができなくなりますので、過食への欲求から気持ちをそらすことに有効です。
過度に自分に期待したり、理想を高く掲げない
摂食障害を持つ女性は、自分に対して過剰に厳しいハードルを課してしまいがちで、いわゆる「頑張り屋さん」であったり「完璧主義者」であることが多いです。自分が太っていると思い悩んでしまうと、芸能人やモデルなど一般的ではない人たちや、時には空想上のキャラクターなどと自分を比べてしまったり、標準体型なのにひどく肥満状態であるように感じてしまったりします。
「自分を客観的に見る」ということが難しい状態になっているため、まずは自分に対して少しハードルを下げてあげたり、今の自分でもいいと許してあげたりすることが大切です。ありもしない理想を追い続けるだけでは、なかなか状況は改善できません。
リラックスする方法を見つける
ストレスを感じている状態になると、息が上がる・脈が速くなるなど、体が一種の“緊張状態”に陥ります。そういった状態になると、普段は思わないことを考えてしまったり、冷静に物事を判断できなかったりしてしまいがちです。過食に走るのもそのうちの一つで、あとから冷静になって「どうしてあんなに食べてしまったんだろう…」と落ち込んでしまいます。
体のストレス状態を解消するには、リラックスできる環境や行動が大切です。静かな場所で深呼吸をしてみたり、落ち着ける音楽を聴いたり、お気に入りの香りをアロマで楽しんだりすることがおすすめです。また、ただただ体の疲れをいやすために睡眠をとる、というのも有効な方法と言えます。
過食症に多く見られるチューイング行為
摂食障害の方で見られることが多いのが、食べ物を口に入れて噛むだけで、飲み込まずに吐き出してしまうチューイング行為です。チューイング行為の背景には「食べたい、けれど太りたくない」という気持ちが働いており、過食症でよく見られる行為です。チューイングは脳が食べたと認識し、胃が消化をしようとし始めるため、自律神経の乱れや体の不調が生じます。どんなに食べても「太らない」ことが嬉しくなりチューイングを繰り返した場合、過食嘔吐につながることもありますから、チューイング行為は避けるべき。
チューイングしやすい食べ物というのは特にこれといったものはありません。チューイング行為は過食願望をコントロールするための方法ではありません。立派な摂食障害の行動であると認識しましょう。