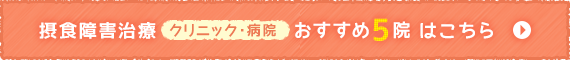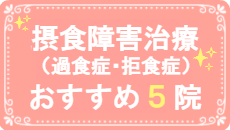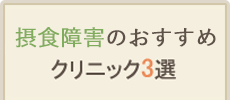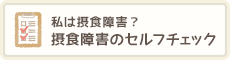体重が何キロだと摂食障害なの?

痩せすぎは要注意!拒食症と過食症で体重との向き合い方が違います。
摂食障害は体重だけでは断定することはできませんが、拒食症に関しては数式があります。ここでは、拒食症かどうか判断する体重計算の方法や、過食症と体重の関係性について解説。体重計が摂食障害の治療に必要かどうかについてもまとめています。摂食障害で悩んでいる人や、その周囲の人に見てほしい内容です。
拒食症かどうかを判断する体重計算
-
拒食症は標準体重よりー20%以上痩せている
自分の意思とは関係なくご飯を食べることが出来なくなり、体重が減ってしまう拒食症。拒食症と診断される場合、標準体重より20%痩せていることが目安になります。ここでは、標準体重の計算方法と拒食症かどうか判断する体重計算をご紹介。
-
標準体重の出し方
標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
- 身長が160cmの場合
1.6(m)×1.6(m)×22=56.32kg - 身長が150cmの場合
1.5(m)×1.5(m)×22=49.50kg - 身長が140cmの場合
1.4(m)×1.4(m)×22=43.12kg
- 身長が160cmの場合
-
拒食症かどうか判断する計算方法
先ほど出した標準体重より20%以上痩せている場合、拒食症の診断目安になります。
- 身長160cmの標準体重は56.32kg
→そのー20%は、45.05kg - 身長150cmの標準体重は49.50 kg
→そのー20%は、39.60kg - 身長140cmの標準体重は43.12 kg
→そのー20%は、34.49kg
- 身長160cmの標準体重は56.32kg
この計算方法は日本医師会のホームページからを参考にしています。
なぜ22をかけるのかというと、肥満指数を表すBMIの理想的な値が22だからです。BMI22は統計上「最も病気になりにくい」という結果が出ています。
もし20%以上痩せている状態が3ヶ月以上続くようであれば、拒食症の可能性があります。一度クリニックに足を運び、医師に診てもらうようにしましょう。
過食症は体重から割り出せるのか?
拒食症と違って、過食症は体重だけで症状を断定するのは非常に難しい病気です。過食症は食欲をコントロールできず異常な量を食べ続けるのが特徴。しかし、過食症の人で明らかに太っている人はわずかしかいません。
多くの場合、標準体重よりも痩せています。なぜなら過食症の人は、食べた後に嘔吐や下剤を使ってとにかく出そうとするからです。過食症の場合は体重だけでなく、「自己嘔吐はしていないか」「下剤を乱用していないか」「異常な量の食べ物を摂取していないか」などを合わせて判断しないといけません。
過食症になるとどうしても嘔吐や下剤を使用しているという事実から目を背けてしまいます。でも勇気を出して身近な人や医師に相談できれば、治療への第一歩です。周囲の人も体重に限らず、食べ物の量や嘔吐していないかを注意深く見つめてあげてください。
摂食障害の人は体重を計るべき?やめるべき?
結論から言うと、摂食障害の人は体重を計るべきではありません。摂食障害の人は、家に体重計があると治療が成功しないと言われています。
摂食障害の人が一番恐れているのは「体重が増えること」。体重が増えていたとしたら、自己嫌悪になってしまうでしょう。クリニックで診察を受けた後、多くの人は「頑張って食事を摂ろう」「今日は嘔吐しないようにするぞ!」と思います。医師の話を聞けば、自分の病気に向き合う気持ちになれるからです。
ところが、家に帰って体重を計って100gでも増えているとわかったら…。もう、医師からもらったアドバイスも病気にうち勝つ決意も、頭の中から全て消え去る可能性が高いのです。その時点でまともに食事を取れなくなり、食べたものを吐いてしまったりします。
摂食障害を抱えている人にとって、体重を計れなくなることは恐怖でしかないかもしれません。それでも、体重計は無くしましょう。数字ばかりに目がいってしまい、体の声を聞けなくなっては、体はボロボロになってしまうばかり。体重に向けていた意識を、少しずつ治療に切り替えていくことが大切なのです。